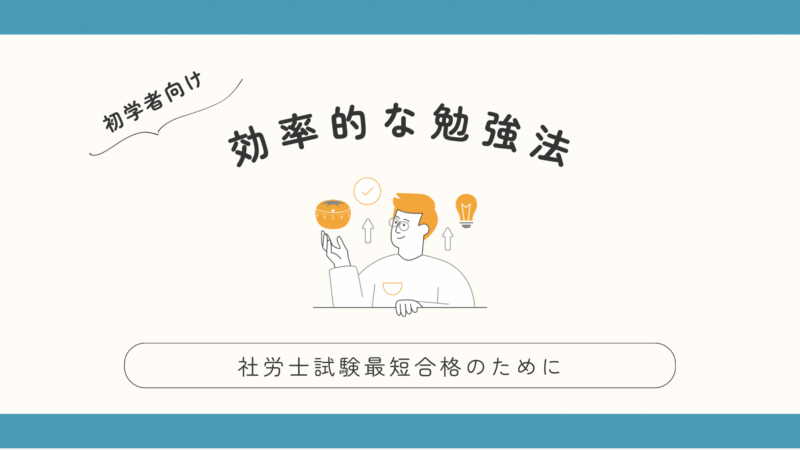「短時間・有期雇用労働法」改正動向と今後の雇用管理への影響 – 社労士試験対策
皆さん、こんにちは。社労士試験に挑戦している受験生の皆さんに、最新の法改正情報をお届けします。今回は「短時間・有期雇用労働法」の改正動向について詳しく解説していきます。
1. 最近の法改正ニュース:パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善強化へ
厚生労働省は、2024年10月に開催された労働政策審議会において、パートタイム・有期雇用労働者と正社員との不合理な待遇差をより一層是正するための法改正案を提示しました。この改正案は、同一労働同一賃金の更なる実効性確保を目指すもので、2023年4月に全面適用された現行法の運用状況を踏まえた見直しとなっています。
改正のポイント
- 事業主に対する説明義務の強化
- 待遇差の合理性判断基準の明確化
- 労働局による助言・指導・勧告権限の拡充
- 待遇差に関する情報開示範囲の拡大
特に注目すべきは、事業主が非正規社員に対して行う待遇差の説明内容を「具体的かつ分かりやすいもの」とすることを明確に義務付ける点です。これまでの運用では、説明が形骸化しているケースが散見されたことを受けての措置です。
2. 社労士試験で押さえておくべき関連知識
短時間・有期雇用労働法(パートタイム・有期雇用労働法)は、社労士試験において頻出の分野です。以下に重要ポイントをまとめました。
| 項目 | 内容 | 試験での出題傾向 |
|---|---|---|
| 法の目的 | 短時間・有期雇用労働者の公正な待遇の確保、雇用管理の改善 | 高頻度(法の趣旨理解) |
| 不合理な待遇差の禁止 (8条) |
職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情を考慮した不合理な待遇差の禁止 | 最重要項目(各種手当の事例) |
| 差別的取扱いの禁止 (9条) |
職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同じ場合の差別的取扱い禁止 | 高頻度(8条との違い) |
| 説明義務 (14条) |
待遇の内容・理由等に関する説明義務 | 中頻度(今後増加の見込み) |
8条の「不合理な待遇差の禁止」と9条の「差別的取扱いの禁止」の違いを明確に理解することは、試験対策として特に重要です。
実務上のポイントとしては、以下の3つの要素に基づいて待遇差の合理性を判断することが重要です:
- 職務内容:業務の内容および責任の程度
- 職務内容・配置の変更範囲:人事異動や昇進・昇格の可能性等
- その他の事情:労使交渉の経緯や労働市場の状況等
3. 関連する社労士試験過去問
【平成30年度 択一式問題】
短時間労働者の待遇の原則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事業主は、短時間労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取扱いをすることは禁止されているが、有期労働契約により使用される労働者であることを理由とする差別的取扱いについては、特段の規制はない。
- 事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間労働者であると認められる者については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施及び福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
- 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果等に応じ、賃金を決定するように努めることとされているが、賃金以外の待遇については、特段の規制はない。
- 事業主は、通常の労働者と職務の内容が同一の短時間労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施及び福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
- 事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の短時間労働者についても、その待遇の相違は、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
正解:4
解説:
選択肢4が正解です。これは短時間労働法(現在の短時間・有期雇用労働法)9条の「差別的取扱いの禁止」に関する記述で、①職務内容が同一であり、かつ②職務内容・配置の変更範囲が通常の労働者と同一と見込まれる短時間労働者について、短時間労働者であることを理由とした差別的取扱いを禁止する規定を正確に表しています。
選択肢1は誤りです。法改正により有期雇用労働者も差別的取扱いの禁止対象となっています。
選択肢2は誤りです。「同視すべき短時間労働者」という表現は法律上の用語ではなく、条件も不正確です。
選択肢3は誤りです。賃金以外の待遇についても均衡待遇の努力義務が課されています。
選択肢5は誤りです。「同視すべき短時間労働者」という表現は不正確で、不合理な待遇差の禁止は全ての短時間・有期雇用労働者に適用されます。
4. 今後の試験対策のポイント
短時間・有期雇用労働法については、今回の改正動向を踏まえると、特に「説明義務」の内容や「待遇差の合理性判断基準」について、令和7年度以降の試験で出題が増える可能性が高いと考えられます。
実際の裁判例(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件など)にも目を通しておくことをお勧めします。これらの判例は、不合理な待遇差の判断における実務上の解釈指針となっています。
試験対策まとめ
- 短時間・有期雇用労働法の8条(不合理な待遇差の禁止)と9条(差別的取扱いの禁止)の要件の違いを明確に理解する
- 「職務内容」「職務内容・配置の変更範囲」「その他の事情」の3要素による判断基準を押さえる
- 今回の法改正によって強化される「説明義務」の内容を理解する
- ガイドラインや裁判例における各種手当ごとの判断事例を学習する
社労士試験の合格を目指す皆さん、最新の法改正動向を押さえつつ、基本的な法律の枠組みをしっかり理解することが何より重要です。一緒に頑張りましょう!
参考資料:厚生労働省「短時間・有期雇用労働法」関連資料、労働政策審議会資料