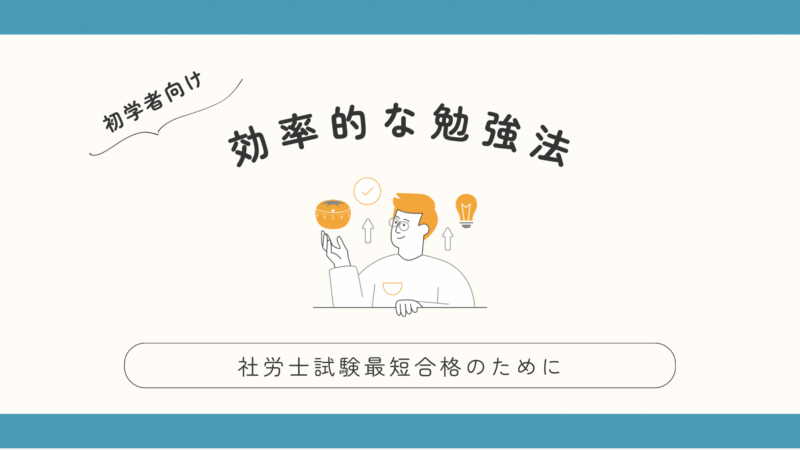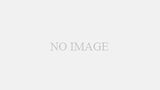【社労士試験】労働基準法「労働時間」の頻出論点まとめ|独学でも得点源にする方法
労働時間が社労士試験で重要な理由
労働基準法の中でも「労働時間」は毎年必ず出題される超頻出テーマです。
とくに「法定労働時間」「時間外労働と割増賃金」「変形労働時間制」は出題率が高く、理解が不十分だと確実に失点につながります。
✅ ポイント:労働時間は暗記だけでなく「条文理解」と「例外処理」を押さえることで得点に直結します。
頻出論点① 所定労働時間と法定労働時間
- 法定労働時間:原則1日8時間・週40時間(労基法第32条)
- 所定労働時間:就業規則や労働契約で定められた時間。法定労働時間を超えてはならない
👉 試験では「所定労働時間=法定労働時間」と誤解させるひっかけ問題が出題されやすいので注意。
頻出論点② 時間外労働・休日労働と割増賃金
- 時間外労働は 36協定 の締結が前提
- 割増率:
- 時間外労働 → 25%以上
- 休日労働 → 35%以上
- 深夜労働(22時~5時) → +25%
👉 よく問われる計算問題:「時間外労働25%+深夜労働25%=50%」を確実に覚えましょう。
頻出論点③ 休憩時間の原則と例外
- 労働6時間を超える → 45分以上
- 労働8時間を超える → 1時間以上
休憩は「労働者が自由に利用できること」が要件。
👉 出題ポイント:分割休憩は労使協定で可能/使用者が業務を命じる休憩は無効。
頻出論点④ 変形労働時間制の理解ポイント
- 1か月単位の変形労働時間制(就業規則等で定める)
- 1年単位の変形労働時間制(労使協定+行政官庁への届出が必要)
- フレックスタイム制(清算期間は1か月以内、2021年改正で3か月まで拡大)
👉 条文が複雑なので「表にまとめて整理」するのがおすすめです。
効率的な暗記法と直前対策
- 数字をまとめて暗記:「1日8時間・週40時間・休憩45分・割増25%」
- 過去問演習で反復:「条文とセットで覚える」ことが得点力につながる
- 直前期の優先度:「例外規定」「割増率」「変形労働時間制の条件」を重点的に確認
👉 私自身も独学時代、過去問を使って「数字カード」を作り、繰り返し復習することで短期間で得点を伸ばせました。
まとめと次のステップ
労働時間は労働基準法の中でも最重要論点であり、確実に得点源にできる分野です。
基本(法定労働時間・休憩・割増賃金)を押さえ、変形労働時間制を整理して理解しておけば、試験本番でも安定した得点が狙えます。
👉 次回は「休日・休暇」の頻出論点を解説します。
関連記事(内部リンク)
CTA(行動喚起)
📥 労働基準法の暗記チェックリストを無料配布中! 学習の抜け漏れ確認にご活用ください。
📅 最新記事を見逃さないよう、ブログの更新通知を受け取りましょう。